先日、ZOOMのB3nというベース用マルチエフェクターのプリセット動画を作成して公開してみました。
ZOOM B3nはマルチエフェクターの中では非常に安価で、それでいて多機能な機材です。B3シリーズが発売されるまで、ZOOMというだけで「安いけど、音色が…」と難色を示していた人は多かったのですが、B3(ギターであればG3)で一気に違和感のないレベルになり、続いて発売される製品も「安価で高品質」を絵に描いたように扱えるものになっています。
今回は、2019年現在最も新しいマルチエフェクター「B3n」にスポットを当て、工場出荷時に内蔵されているプリセットをそのままに演奏してみた動画になります。
プリセットの紹介と解説
それでは今回使用したプリセットについてそれぞれ紹介していきます。書いてみたら非常に長かったので、今回を第1回として、次回と併せて全部紹介できるようにまとめていきます。
なお、録音環境としては動画の一番最初に書いていますが、「5弦ベース→B3n→PC」という『B3nだけを感じてほしい』という狙いのものになっています。
というのも、B3nは1パッチに7エフェクト入れることができるので、実際音の作り込みは高度に行うことができるのです。比較としてLine6の廉価機種「HX Stomp(約7万円)」は同時6エフェクトとなっているので、7エフェクトが決して少ないものではないことがわかります。
00. Rhythm Fusion
オープニングで使用しているドラムパターンですが、これもプリセットから取り出しました。
練習用にも使えるドラムパターンが10種類以上入っているのですが、その中の一つです。本物とまでは行かないものの、ちょっと使いたいという程度には十分な音質だと思います。
01. 013:Rock Slap
Slapと名前はついているものの、2フィンガーで演奏。一通り弾いてみて、最もオーソドックスな音色だったので、オーソドックスな3コードを弾いてみました。普通、パッチNo.1がオーソドックスな物だと思うのですが、そっちはイマイチだったんですよ…
この音色はRockのみならず、Popでも全然問題ないと感じました。ボカロ、アニソン、ロック、ポップと「バンドやろうぜ!」となった時の全方位型エフェクト。ひとまず、はじめましてのバンドだったらこれで行けば良いんじゃないかなと言うくらい、割と万能。
02. 025:RockDist
3フィンガーにも向いているという事だったのですが、思いの外、ローが強く出てしまっていたので数値上の音圧に対して聴覚上のボリュームが合わなかった音色です。要するに、聞こえやすい音量にするとミキサー上で「音量もっと下げてくださいね」という表示が出てしまうというところです。
そこで、B3n自体のボリュームを低めに設定し、アタックの強いスラップで録音しました。なので、実際に他の音色と切り替えて使うとなると、ローの扱いを少し修正しつつボリューム感を調整する必要がありそうですね。
03. 017:GREMLIN
マルチエフェクターを使う上での楽しみの一つ、シンセベースです。今回の動画の中にもいくつか取り入れています。 エフェクトを見ると「アンプヘッド→キャビネット→シンセ」と通常ありえない構図なのも、マルチエフェクターらしいところですね。
このGREMLINは、名前に反して非常に素直で扱いやすい音色でした。 ウケ狙いで入れられるかなと思っていたのですが、「あれ?思ったよりもマトモ??ん??」となっていました。
エフェクトの構成を見ると「SymTlk」が音の主軸になっていることがわかります。 一般的に名前の聞く「オクターバー」よりも使いやすく、奇をてらいつつも様々な音楽に溶け込むポテンシャルがあるんじゃないかと。アタック感も拾いつつ、リリースは短めにとれるので、割とタイトなリズムもいけそうですね。
04. 012:RockDrive
歪み系で指弾きに適した音色は、前述のRockDistではなくてこちらかと。ミッドが強く、音色の反応も早いので、第一印象がビリー・シーンでした。フレーズはそれに触発されたものです。ムズカシイ…。
構成を見ると非常に面白いのがノイズリダクションが一番前に来ている点。コンパクトエフェクターを並べてボードを作ると、ノイズ対策は一番最後になることが多いのですが、この音色では一番最初に持ってくることで、キレイに歪ませているように感じました。
前述のRockDistと音量のレベルが違いますが、それを揃えてしまえば曲の中でキャラクターの違う歪を行ったり来たりできるので重宝しそうです。その中で言えば、この音色は指弾き向きなのかなと感じました。
05. 043:Oct-Fuzz
なんでオクターバーにファズをかけようと思ったんだろう…と首をひねってしまったものの、これも意外と悪くないですね。
弾いていて気付いた点は、コンプを使用していないのに粒が揃いやすいということ。そしてオクターバーの追従性が高いので、総じてゴーストノートもきちんと再生されるという点が気に入った点です。
一見すると使いにくい音色のように感じますが、テクノやボカロの打ち込み系だとこの音色でうまいこと表現できそうなので、曲に合わせて活躍する場所はありそうです。例えばこんな感じとか良いのかなと↓
06. 007:Harmonics
コーラスにリバーブをかけてコンプで潰すという、これまたマルチじゃないとなかなか見ない音作りですな。けど、嫌いじゃない!
ポイントは「最後にコンプ」という点だと思います。これのお蔭で、2フィンガーで弾いた部分のアタック感がよく出ていました。ハーモニクスと混ぜて弾いてみましたが、一定の音量感なのに音色やニュアンスが様々出せるのは弾いていて楽しさがありました。
演奏にはハーモニクスを使用しつつ、開放弦を使っています。通常のベースよりも空気感が出ているので、ソロで弾いても味のある演奏にしやすいのではないかと感じます。
次回で動画のパッチを紹介完了
今回動画を作成するキッカケは、実はオークションに出そうと思ったからというのが一番の理由でした。しかし、弾いてみるとなかなか色んな音色が出せるので、そのうちに楽しくなってきてしまい、『手放すには惜しいぞ!コレ!!』となってきた機材です。そのため、シンセベースなども紹介することにしました。
通常、マルチエフェクターは複数の曲調に併せたり、掛け持ちのバンドが多い時に多用されるかと思います。あとは機材を少なくしたいときとかね。
このB3nはそんな人にあっているのではないかなと思います。理由は、元になっているエフェクターが説明書に記載されているからです。
例えば、SANSAMPのBASS DRIVERは使っているベーシストは多いですが、これをモデリングし、どのエフェクトがこれに相当しているかが分かるようになっています。他のエフェクターもオリジナルがあるものについてはそうですね。だから、ストンプ型のコンパクトエフェクターから引っ越してきたとしても、近い音色を作りやすくなっています。こういうことが出来て2万円とは、本当にスゴい時代になりましたね。
[rakuten no=”4515260017294″ kw=”ZOOM B3n Multi-Effects Processor”]
後半はこちら↓





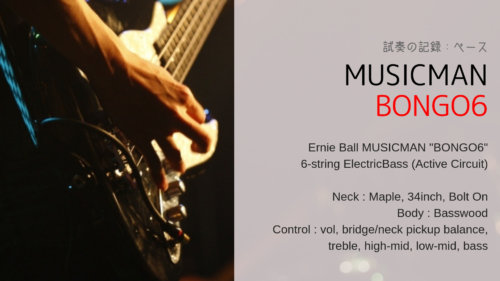
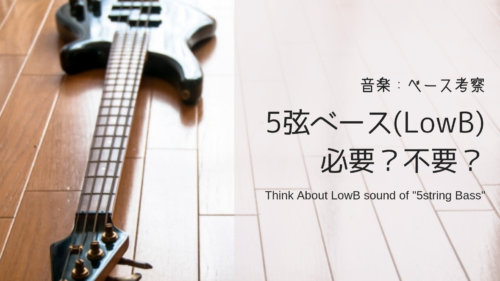


コメント